一般論説No.2 環境問題の根源



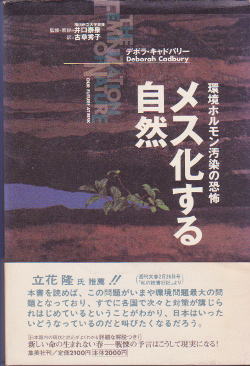

この論説は境港ライオンズクラブ会報 No.227号(平成9年8月)「環境問題特集号」で発表した「地球生命圏-ガイアの科学」を導入編とし、環境問題全体にわたり新たに体系づけて構成したものである。
導入
一般論説No.2 環境問題の根源



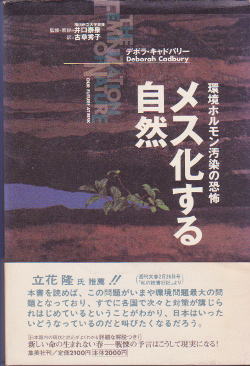

この論説は境港ライオンズクラブ会報 No.227号(平成9年8月)「環境問題特集号」で発表した「地球生命圏-ガイアの科学」を導入編とし、環境問題全体にわたり新たに体系づけて構成したものである。
導入
今、各種のグループ、団体、クラブ、組織、あるいはNGOや地方自治体などが様々な角度から「環境問題」に取り組んでいる。それらの中には大気の汚染防止、水質の保全、生態系の維持、再生に関する分野から、資源の愛護、同リサイクル、環境美化にも及び、さらには自然との共生を基礎とする簡素な生活運動にまで発展拡張し、相互に絡み合い、複雑な様相を呈し、時にはイデオロギーまで介在して、環境問題の本質を見失う恐れさえ感じられる。
そこで、この機会に「環境問題」に携わる一人一人が事の本質を改めて理解、確認して、共通の基盤にたってそれぞれの分野で問題の解決に努力することが重要不可欠と考え、必読の文献を紹介しながら、その要約を通して環境問題の根源について述べてみたい。
本論
その一:「ガイアの科学」 地球生命圏 (J.E.ラブロック)
要約
始めに「カオス」(混沌)があった。この「カオス」の中から重たいものが次第に下がっていって、胸の広い大地の女神「ガイヤ」が生まれた。これはギリシャ神話の世界の始まりである。「ガイヤ」はギリシャ神話の世界に現れた最初の神であり、大地の女神であると同時に、森羅万象を司る神々の根源的存在でもある。自ら生んだウランヌス(天空の神)と交わってクロノスを生み、後のジュピター、ネプチューン、ブルート三兄弟による世界支配態勢確立の後押しをした。
1970年代、NASAの火星探査プロジェクトに参加していた分析化学者のジェームス・ラブロックが「地球環境と地上に生きる生命体は、一体化した自己調整システムを形成している」ことを指摘した時、彼の友人の小説家ウイリアム・ゴールディングはそれを「ガイヤの仮説」と呼ぶことを進言した。それは地球の大気組成や気候がその上に住む生命体の生存に都合の良い状態に自己調節され、保持されていく有様が、あたかも女神「ガイア」が地上に住む生き物の生存のため力を行使しているように見えるというのである。
最近急速に発達を見せている複雑性の科学からラブロックの主張する「地球が見せるホメオシタス」(恒常性)現象を側面から解き明かしてくれるようになった。「ガイアの仮説」が「ガイアの理論」になるのは時間の問題である。
ネガティブ・フイードバック(負帰還)
地球の気温は炭酸ガスの濃度によるよりは雲の発生度のほうが遥かに大きい影響を示す。雲の発生には海洋プランクトンの働きが必要条件で、海洋中の植物プランクトンの多くは硫化ジメチルと呼ばれる気体の化合物を生産し、これが大気中で酸化されて硫酸塩エアゾルを作り、その周りに水蒸気が凝結して雲の粒子が作られる。地球が暖まればプランクトンの活動が活発になり雲の量が増えて地球を冷やす力が働く。このようなループを通して働くネガティブ・フィードバック(負帰還)効果が地球の恒常性の秘密である。
適用
熱帯林の乱伐も、伐採される植物相よりはそれにより生じる土壌微生物相の破壊のほうがはるかに問題である。また大規模の放牧により草の根(生物相)までが食みつくされた後の砂漠化は修復困難である。
他方、動物の有毒重金属の含有の問題については、人類の工業活動が盛んになる前から、マグロの脳にはかなりの濃度の水銀が、そして牡蠣には亜鉛、銅、カドミウムが、海藻には砒素が含まれていた。これは自然のバランスであり、人類社会だけが有毒重金属の真空地帯を作ろうと試みるのは文明の進化を阻む有害な行為である。
大自然の環境破壊の歴史
「ガイア」は人間の愚かな行ないがもたらす環境破壊以上のすざましい環境変化を過去に何度も経験している。大隕石の衝突、氷河時代、あるいは「ノアの洪水」に象徴されるような大気の大変動にも対処しつつ、自律的にその時々に最適の生態系システムを組みあげ、またはそれに適応するように環境を引き寄せ安定化させる働きを続けてきた。今日、現在、どこかの海底で海底火山が爆発し、膨大な硫化物を吐き出して広大な海面を黄色に染めているかも知れない。しかし、「ガイア」はこれを包み込み、なんの痕跡も残さない。
ホメオシタス(恒常性)のづれ
人類の文明活動の急進展、爆発的な人口増加は地球環境に様々な影響を与えるが、40億年にわたって働き続けてきた自己調節機能がそれで破壊されるほど「ガイア」はひ弱ではない。人類の行き過ぎた活動の影響は「ガイア」の恒常性に若干のづれを生じさせるかも知れないが、「ガイア」はそれを包み込んで、更なる進化を続けていくことができよう。
しかし、この若干のづれが人類にとってどのような意味を持つかわ「ガイア」の知るところではない。「ガイア」が40億年にわたり守り育ててきたのは地上の全生命体を組込んで働く、複雑で広大な自己創造ネットワークであって、その上に乗って栄枯盛衰を繰り返す個々の生物種ではないからである。「ガイア」にとっては人類の文明社会も、その構成素子の一つ以外の何ものでもない。
即ち、我々が直面しているのは「ガイア」の危機でも地球の破局でもない、人類文明が作り出した人類文明の危機なのである。
自然が新しく生まれ変わり活性を維持していくためには、山火事や洪水が「ガイア」のサイクル要素としてそれなりの積極的な役割を担っているように、森林伐採や焼き畑もそれが自然のリズムに見合って節度を保ちつつ行なわれる限り決して悪ではない。問題は伐採よりもその後の土壌微生物の保全など自然の成長力の維持増進のためどれだけのアフターケアがなされるかにある。それがたちまち「割り箸禁止運動」や「熱帯雨林伐採國への貿易制裁」などに短縮してしまうことに現代の環境運動の病根が潜んでいるようである。
地球温暖化
「地球温暖化」という言葉が飛び交うようになったのは1988年6月、NASAのゴダート宇宙研究所に勤めるJ.E.ハンセン教授が上院の公聴会で証言した「CO2による地球の温暖化はすでに始まっていることを99%確信している」と言った以来である。。同年、7月に地球温暖化防止法案が米国議会に提出され、気候変動に関する政府間パネル(通称、IPCC)が設立された。
しかし、CO2による地球温暖化は科学的に証明されているわけではない。マサチュセッツ工科大学のディック・リンツエン教授は「CO2の濃度が高まれば雲が増へる。雲は冷却効果を持ち、温度を下げる働きをする。温暖化のシミュレーションにはその要素が加えられてないので、CO2の増加が温暖化をもたらすとは断言できない、その逆に、寒冷化をもたらすかも知れない」と。さらに、人類が大気中に放出したCO2の論理的な量と、実際に大気中で観測できるCO2の量の間には著しい乖離が見られるという報告もある。具体的には約100億トンのCO2がどこかに消えてしまっているのだ。森林か海洋か、それともなにか別の作因によるのか、人類はまだCO2の循環システムを完全には把握していないのである。
それにもかかわらず、CO2の地球温暖化が"真理"と見なされ、その排出削減が国際的なコンセンサスになったのは工業先進国の大きなたくらみがあるからである。
それは、1990年、ヒューストンで開催された経済サミットの最終コミュニケに明かである。そこには次のように書かれている。即ち。「工業先進国としての我々は、環境問題に対処する際に、指導者としての責任を有している。修正不能な環境破壊という脅威を前にした今、十分に科学的な根拠が無かったとしても、それは行動を先送りする理由にはならない。力強い市場志向経済こそ環境保護を成功させる最大の手段である」と。
要するに、CO2地球温暖化説は先進国が途上国をコントロールするための切り札なのだ。急激な人口増加(中国、インド)、工業化(中国をはじめ東洋東南アジア等)、森林資源の消滅(アマゾンやボルネオ等)等々、それらを地球環境保全という正論を用いることにより抑制し、先進国が望む国際秩序の枠内に収めることこそが真に狙いであり、正体でもある。それ以外のなのももでもない。
しかし、1985年以来、大気中の炭酸ガスの濃度が着実に増え続けていること、炭酸ガスが温室効果を示すことは明らかな事実である。
南太平洋に浮かぶ島、ツバルの住民は2002年から移民を開始する。京都会議でアメリカが「自国の経済に悪影響を与えるCO2削減に関する条約は認めない」、「地球の温暖化の影響は理論的に立証されてない」とした地球温暖化による海面の上昇で島が沈むためである。
温暖化、海面上昇のシナリオが正しければ、この増加が海岸線近くで営なまれている文明社会に破壊をもたらす可能性は否定できない。しかし、一方では、炭酸ガスの濃度の増加で植物の成長を助け、農業にはプラスに働く面もあろう。また、温暖化はカナダやシベリアなどの寒冷地にはむしろ新しい文明の可能性を恵むかも知れない。
現時点では炭酸ガスの濃度の増加がもたらすプラス、マイナスの効果はいずれも仮説の域を出ないが、これは決して"地球の破局"を意味するものではない。しかし、人類の活動で大気組成に急激な変化を起こせば、「ガイア」の恒常性に悪影響を与える可能性は否定できない。そしてそれが局地的および一時的に人類社会に壊滅的な事態を招くかも知れないが、「ガイア」の活動(即ち、地球そのもの)にとっては単なるイベントに過ぎない。
しかし、温暖化による海面上昇により次のような事態が生じることは間違いない。即ち、現在の世界では、人口の過度の集中が大河川系に沿った低地の海岸地方に起きており、全人類の約三割以上が海岸線から60キロメートルな内に住んでいる。僅かに25センチメートル平均水面が上昇するだけで重大な影響が起こるだろう。多くの国で国内避難民が増大し、大きな社会問題を発生する。
またオゾン層の破壊により、紫外線が爆発的に増え、人間の免疫系統が弱まり、特に、熱帯地方では爆発的な人口増加と都市化が伝統的な文化様式を疎外する。そして細菌、ウイルスが活発に活動し、病気が蔓延するようになろう。
地球温暖化の影響に関する国際的な取り組みについて、
19292年、ブラジルのリオで国連環境開発会議(UNCED)(いわゆる地球環境サミット)が開催され、「気候変動枠組条約」と「生物の多様性に関する条約」が締結された(174ケ国)。
1995年、ベルリンで議定書作成のための会議(COP)が開催された、
ここで、排出削減の対象となる六つのガスの中で最も重要な二酸化炭素は1997年、全世界で62億7000万屯排出されており、その4分の1は米国一国で排出され、次にEU全体、第三位に中国、そしてロシア、日本、インドの順となっている。日本は一人当たりの量で計れば中国の四倍を排出している。
具体的な数値で目標設定を行なうのは24の先進国とロシア、ポーランド、ハンガリーなど11ケ国の計35ケ国と1機構である。
1997年、京都で行なわれたCOP3(京都会議)で具体的な数値が決まった。即ち、先進各国が削減する数値目標を日本は6%。米国は7%、EUは全体で8%削減することになった。ここで問題となるのは主用国のこの削減目標に積算根拠が殆どないまま、全て政治的妥協として決まったことである。
さらに、開発途上国の扱いについて、具体的な数値には応じられないにしても、せめて努力目標を設定すべきという米国の強い要求にもかかわらず、急速に工業化を進めている中国、インド、ブラジルやこの三国に続く国々は、本来行なう義務のある産業化の手を縛られてしまうので、具体的な数値の約束はできないという立場である。即ち、京都会議では途上国からは何らの約束を取り付けることが出来なかったのである。
しかし、幾つかの前進がみられ、それは国家間で排出量の取引き(多量の排出規制を行なう国に金額を支払、自国の規制を緩和する手法)が認められえたことにある(クリーン開発メカニズムと呼ぶ)。 もう一つは「吸収源」という仕組みで、新たな植林の効果等を排出量削減の数値に計上(減算)してよいということである。この「吸収源」には海藻類も含まれる。
200年、オランダのハーグで開かれたCOP6の交渉では、参加国の意見の対立は解消できず、2001年に、米国のブッシュ新政権は京都議定書を支持しない姿勢を明示した。
その理由の一つと考えられるのは、地球の温暖化と海面上昇との相関関係が必ずしも論理的に論証されたものでなく、化石燃料の使用の増大が炭酸ガスの増大を招き、それが即ち、地球の温暖化、そして海面の上昇というありきたりの論法でなく。例えば、NASAの研究者が衛星データを利用して実際に計算した南極大陸の中央部の温度が10年で0.4度も低下しているという事実に基づき、巷間叫ばれている「温暖化」とは本当のところはどうなのかという大きな疑問があるのである。化石燃料の使用削減を地球の温暖化防止の切り札とし、それにより「海面変動」を抑制するという論理には大きな疑問がある。
参考:2002年にロイターが公開した四枚の航空写真(南極半島の先端から少し右下の場所にある「氷棚ラーセンB」の写真)がある。それによると南極大陸の内部は温度が下がり つつあり、氷の厚味も増してしる。しかし南極半島では氷が溶け出している。つまり、南極大陸の岩盤の上ではどんどん氷が厚くなり、周辺部の海の上にある氷が溶けている のである、またNASAのゴーダ度宇宙センターの研究者が衛星画像を分析調査した結果、南半球の氷が1979年から21年間にわたって増加し続け、逆に、北極の氷が減ってい ることが判明した。これらの事象をまとめると次のようになる。
・南極の大陸上は氷が厚くなっている。
・南極半島など、周辺部の海面上では氷が溶け出している。
・北極圏では氷が溶け出している。(しかし氷塊の3/5は水中にあるので、地球全体の海面の上昇に及ぼす影響は少ない。)
・極地全体でみると、氷の増えている地域の面積が減っている地域の二倍ある。 このことはスエーデンなどの北辺諸国でも内陸部
の氷が厚くなっている事実から分かる。。
即ち、今、地球上で起こっていることは地球温暖化というシナリオから期待されたものとは異なり、現実はもっと複雑である、ということである。
2002年3月、南極のドーム・コンコルディアの地点で國際調査団が2865mまで氷土を掘り下げて、およそ53万年まえの氷を切り出したとの発表があった。
ここ約30万年程の間に氷河期と間氷期が6万年ほどの長さで変化していることは早くから推定されてきたことで、現在は先の氷河期の「後氷期」と呼ばれているが、それは次の氷河期までの「間氷期」と考えられる。地球は局所的な気温の上昇こそみられるが、つまりは地球全体として冷えつつあるのである。
今回の調査により、掘り出した氷の状態と気候の変動の関係の分析が進めば、大気中の二酸化炭素が気候に及ぼす影響が明らかになるであろう。
2001年、ドイツのボンで行なわれたCOP6継続交渉で、京都議定書の運用ルールに関する議長案が採択された。それは先進国の合計排出量(1990年基準)が全先進国排出量の55%以上になった時の90日後に発効すると定めている。 1990年の先進国の全排出量全体に占める割合は米国が36.1%、EUが24.2%(うちドイツ、7.4パーセント、英国、4.3%)、ロシアが17.4%、日本が8.5%、カナダが3.3%、豪州が2.1%などである。
米国は2010年までの総排出量を35%増とすることを明かにした。これは今後10年間に米国の国内総生産(GOP)比で18%の排出を削減するという独自の目標を明示したものであるが、これは実質的に1990年比で35%の排出量の増大となることを認めた形となった。
環境問題対策および活動
地域において行なう環境問題対策とは、「地球に優しく」などの擬態を弄することなく、「ガイア」の理論、特に、フィードバック効果に学び、リサイクルを開発、助勢して、システム内で多様な冗長性に富んだ各種の無限回帰ループを張り巡らせることが重要である。 このループにより、例えば、流れが大きくなろうとすると、それを抑える逆の力が自動的にかかってシステムを安定化させる。いわゆる、負のフィードバック効果を期待できるようにする。この効果をうまく働かせるため、エントロピーの法則に従い、所要時間の短い小さなループを多数構築することが重要である。
リサイクルはそれにより回収される資源のエネルギーとそれに要するエネルギー(集積、搬入、輸送のマン・ナワー、電気、ガソリン等エネルギーの消費等)との相関関係を無視することはできない。(幼稚園や小学校の低学年の児童に対して物の大切さを教育する意味での「割り箸回収運動」はそれなりの意味もあるが、エントロピーの法則から見ても有意義な活動とは考えられない。)
さらに積極的には、文明活動に見合うほどに周辺の生態系の活動を活性化させることが重要である。
海洋は巨大なシンクで、海流、潮汐、対流、海面からの蒸発を通してあらゆる元素のリサイクルに直接関与しているばかりでなく、熱や物質の巨大なシンクとして恒常性の保持に大きく寄与している。また、海岸近くの藍藻類の光合成やサンゴやプランクトンのような海洋微生物の炭酸ガスの消化および石灰作用が恒常性の維持に大きく寄与している。
この母なる海の水質の汚染防止とその浄化、および複雑な海洋生態系の活性化が環境問題の根源をなす柱である。
最近はやりの"地球に優しい"とかのキャッチフレーズは地球をか弱い被害者に仕立て、人類をその保護者に擬するような、自然に対する傲慢な姿勢が気に懸かる。
元駐タイ大使の岡崎久彦氏は20世紀を”悔恨の世紀”と総括し、「失なわなかったものを再確認すること、不必要とわかったものを捨て去ること」を出発点として21世紀が希望の世紀に生まれ変ることに熱い期待を表明している。
(注) エントロピーの法則:本来はエネルギーの状態にかかわる物理量、即ち、放置すれば増えることはあっても減ることのない量をいう。
事例研究 :「干拓の先進国オランダに見る環境保護の配慮」
一般に、複式干拓方式は農地を造成し、農業用水を生み出し、災害から地域を守る一石二鳥のメリットがあると云われてきた。しかしこれには既存の生態系を根絶させる大きなデメリットがあることが知られている。
この複式干拓方式の本家、オランダには5.000以上の堤防式干拓地があるという。その中で最大のものは1920年に着工して12年後に完成した30キロの大堤防(締切堤防)で北海に臨むワッデン海の東南部を断ち切って造られた淡水湖「アイセル湖」である。 それは何時でも干拓して農地にできるが現在はその必要がないので湖のままにして、ウナギや水鳥の天国にして放置してある。 観光開発等で環境が汚染されないような法制が整備されているのは勿論である。またこの湖は国民全員のためのものなので、一部の湖岸漁業者による漁業権の主張などは論外である。このように、当初は農地造成目的の干拓地についてもその土地利用は環境改善的な利用に移行しつつあるのがオランダやドイツを始めとする欧州先進国の現状である。
オランダの堤防ずくりは我が国のコンクリート固めとは異なり、自然石を据え、柳の枝を束ねたものをクッションにして次の石を重ねる。オランダは殆どの国土が水面下の平坦地(ネーデルランド、即ち、低い土地)なので石がなく、わざわざ近隣諸国から購入してまでこれらの土木工事に供している。この工法のため、湖内でプランクトンが繁殖し、魚が増え、水鳥が多い。 このオランダ式工法の自然石主義(租だ工法)は生態系の配慮がその目的である。
この巨大な淡水湖はオランダの大きな財産であり、さらには精神の糧でもあるという。そのままにしてなんらの経済的利益を期待しないというのは、環境保全という価値体系の大義に関するオランダ人の先進的な精神を示すものといへよう。
我が国においても1990年代当初に、環境庁が「新たな環境保全、創造政策のあり方」について閉鎖性水域等における破壊された自然を取り戻すための指針を策定した。また一部地方においてはコンクリート堤防の土盛り、柳の植樹、浅瀬の造成および自然石の活用により昔の川岸の復活を試みて成功している自治体が見られるようになってきた。
その他、環境保全の「地球温暖化問題」に対するオランダの取組みについて述べれば、1990年、ハグーで開催された世界の環境大臣会議で、ミティゲーション(環境への影響を緩和する行為)として二酸化炭素の排出量の制限についてオランダが会議をリードし、20%の削減を提案したが各国の同意が得らなかった。しかし、オランダは独自にその基準達成を図り、ジーゼル油1リットルにつき10.8セントの税金をかけ、その税収を対策費に当てることにしている。まさに風車に向うドンキホーテの役割を演じる愚直な姿勢を貫いている。
我が国にあっても、欧米で行なわれているダムや堤防の撤去、河川の蛇行化、護岸を自然な植生に戻したり、都市臨界部の干潟を復元する事業等に見習い、平成13年7月に首相の私的懇談会「二十一世紀【環」(わ)の国】づくり会議」がこの事業の推進を打ち出した。今後の公共事業は従来のものが周辺の生態系や環境を一変させる場合が少なくなかったのに対して、「自然共生」に転換し、自然本来の特質を最大限に生かし、自然の再生と修復を目指すようになる。いや、遅まきながらそうしなければならな程、我が国の自然破壊は進んでいる。
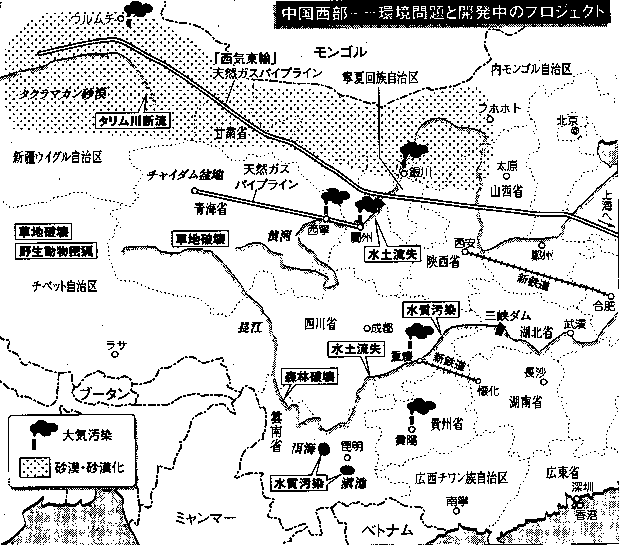
そのニ:化学薬品−自然均衡の恐るべき破壊要因
「沈黙の春」 (レイチェル・カルソン)
梗概
レイチェル・カーソンは早くも1960年に農薬の公害問題を先取りして世に提示した。農薬を含めて殺虫剤・殺菌剤は人間から見て”有害”な生物群を排除するために開発された。そもそもの問題はこの”有害”という定義に含まれている。
自然界全体から見るならば多種多様な生物たちが食ったり食われたりしながら、それなりに安定した生態系をつくっている。人間にとっての”有害”な生物もその生態系の一部をなす構成要素にほかならない。そして特定の種属だけが過度に増え過ぎることがないよう、抑制する自然界の条件が整えられている。
人間がこのタブーに挑戦してこれを破ったのである。この生態系の中の一種ないし数種を撲滅することは全体のバランスを崩し、終局的には生態系の大規模な崩壊を引起すことになる。
たしかに化学農薬の開発は農民にとって未曾有の福音というべきだったが、しかし害虫よりもさらに厄介な相手-病原菌をめぐりさらに厄介な難題が生じた。それは薬品に対する抵抗性の問題で、強力な薬品の散布下でも一部の系統が生き残り、再び増殖を始める。即ち、農薬の洗礼をくぐり抜け、その抵抗性を子孫に遺伝する。そのため更に強力な農薬が必要となり、このようなことが繰りかえされ、いわゆる多農薬農法にゆきつかざるを得なくなった。
化学薬品の広域散布(空中散布を含め)により蝶、とんぼ、蝉を始め各種の小鳥を含む大型の生物は死に絶え、沈黙の春が到来したが、一方において強力化した薬品の成分は作物の内部に蓄積され、いわゆる残留農薬が生じるのである。これが人体に入り蓄積され、毒作用を表す。それとは別に強力化した農薬が作物そのものへの毒として働き、かんじんの作物の順調な成長を阻害することである。
農薬を薄めると撲滅対象の病原菌が再び蘇り、それにより作物が脅かされる。農薬を強めれば上述の結果を招来する。もう絶対絶命の破局が目前に迫っている。
このように、化学薬品により喚起されたこの困惑は、文明そのものが内包する矛盾にほかならない。その解決策は依然として暗中模索の中にある。
「事例報告」 恐るべきべき中国の環境の悪化
2001年の報告例: 中国の甘粛省の辺境の村、八隊(パドイ)村は150mの川幅を持つ黄河上流のほとりにある。そこには発育不全の子供が多数見られた。母親の膝に抱かれていた1歳ほどに見える赤ん坊は八歳だという。顔だけみれば八歳から十歳に見えるがその身体は均整のとれたままミニチュア化されている。その振るまいも赤ん坊で、知能の発達も遅れ、発する言語も極めて限定されていた。この村に住む181人の住民の半分がなんらかの重大な身体的障害を持っていおて、殆ど全ての農民が四十代で若死にしている。
その原因はすぐ上流にある肥料工場が川に流す廃水で、この川が八隊村の唯一の飲み水を含む水源であった。 ある農民は「この川は黄河という名だが、水位が下がれば黒河だ」といっていたと。
中国奥地の辺境でさえこのような状況が随所で頻発していることを考えれば、中国本土の東海岸沿いの急激な工業および経済発展地域における環境の悪化は恐ろしい状態で進行している。 いまや、中国全体におよぶ急速な工業化が史上、類を見ない最悪の環境を作り出している。そして大量の未処理の工業廃水が揚子江や黄河を介して東支那海や黄海に流れ込んでいる。海洋生物、特に魚類に対する影響は現在の所、科学的および統計的なデータはないが、決して無視できるものではなかろう。 風は偏西風にのって中国から流れてくる。日本海の魚の多くは東支那海および黄海を回遊し、対馬海峡を通して日本海に至る。
さらには中国奥地における大規模なダムの建設および森林の伐採により多量の泥土が揚子江に流れ込み、東支那海の大陸棚の海洋環境に著しい変化を与えている。近年における漁獲量の大幅な激減は乱獲以外にこのような海洋の汚染という要素も考慮しなければなるまい。
世界保健機構(WHO)と世界銀行の概算によれば、毎年150万人のアジア人が大気の汚染で死亡し、その他50万人が汚染水と悪衛生状態のため死亡しているとしている。
その三:衝撃の環境ホルモン 「奪われし未来」(シーア・コルボーン 外)
梗概
巣を作らない鷲、孵化しないワニやカモメの卵、子を産まないミンク、アザラシやイルカの大量死、そして人間の精子の数の激減。地球を覆う「生命の衰退」の元凶である「人体に及ぼす合成化学物質の有害な影響」を膨大な科学的データを駆使して追及したこの報告書の重要性はいまさら多言を要しない。
ごみ消却所周辺は勿論、海洋哺乳類にまでその汚染が拡大しているダイオキシン類、身近な食品をはじめ、幼児の脂肪組織や母乳、ペンギンや北極熊の脂肪組織、さらには降雨の中にすら混入しているPCB(ポリ塩化ビフェニール)類など枚挙にいとまがない。
特に留意すべきはこのような汚染物質が生態系内にはりめぐらせれた「食物連鎖」を介して地球の津々浦々まで蔓延している現象である。化学物質の「生体濃縮」も由々しい問題である。
ホルモン撹乱物質(環境ホルモン)
・合成エストロゲン DES(ジェチルスチルベストール-流産予防薬-癌を誘発))
子宮内でDESに暴露したオスはメス同様の被害を受け、様々な生殖器障害を生じる。奇形化した精子、生殖力の減退、性器の腫瘍等)
・サリドマイド(妊婦の精神安定剤、つわり抑制薬) アザラシ状体躯の原因
・DDT(殺虫剤として開発、理由は依然として謎のままだが、人体はなぜかDDTやDSEを天然のステロイド・ホルモンとして取り違えてしまう のだ)
・ダイオキシン(その毒性は砒素の数千倍に相当し、合成化学物質の中で「札つきの厄介もの」の異名を取ってきた。ところが大方の思惑 に反してダイオキシンの恐ろしさはその発ガン性にはなく、新たに浮上してきたのは天然ホルモンの作用を撹乱するという 危険性だった)。
・PCB(安定性と揮発性に加え、脂肪への著しい親和性を兼ね備えた有毒物質。工場周辺の湖に排出されたPC‐153はミジンコの脂肪に しっかり収まり、次にアミと呼ばれる小さな甲殻類の餌になり、食物連鎖の新たな旅路につくのである)
・オレンジ剤(ベトナム戦争で米軍は1900万ガロンの合成除草剤を15000平方メートルの山林地帯に散布した。これがオレンジ剤であった 。ベトナム帰還兵とその家族に癌をはじめ子供の身体障害におよぶ疾病が多発した。)
・CFC(クロロフォルオカーボン) オゾンホールの出現により地球の大気に劇的な影響を及ぼしている。
このほかにも最近、優れた雑燃剤として家具や家電製品に使用されている臭化ビフェニルエーテルが甲状腺ホルモンの働きを撹乱したり、胎児期や新生児期にさらされると知能低下をもたらす等が明らかになった。その汚染実態調査の結果、最も高濃度に蓄積していたのは近海はまちで、次いでブリやサケが高く、遠洋マグロは低い数値であった。魚類の雑燃剤汚染はダイオキシン類の汚染の百から二百倍の汚染濃度に達しているとされる。人体への影響の程度についてはまだ十分なデータはないが、世界で年間五万屯以上大量に生産されているので、その影響の究明と共に環境汚染対策が求められる。
結言
人類は経済発展を望み、生活の便宜性を追求する限り、この恐るべき化学物質から逃げおおせることはできない。実際、これら化学物質は極めて有害で、その影響も益々増幅されていくことが裏付けられ、汚染は誕生と共に、あるいは既に母胎にいる時から始まっている。文明生活に対する人類の基本姿勢を改めない限り、この状態は一生涯変ることなくさらに深刻化する。
特に、人体に対しては精子の減少、生殖器異常、乳がん、前立腺がんなどホルモンに誘発された癌、あるいは多動症や注意散漫といった子供に見られる精神障害、そして野生生物の発育および生殖異常等の現象が益々拡大していくのである。
その四:環境汚染が生んだ新種の猛毒プランクトン
「川が死で満ちるとき」 (ロドニー・パーカー)
梗概
長年、人間が垂れ流してきた様々な排水による河川の汚染とそれに伴う富養化を引き金として恐るべき微生物が爆発的に発生した。それは前代未聞の人間に襲いかかる新種の猛毒プランクトン(フィエステリア・ピシシンダー)である。
最初の発生は米国ノースカロナイナ州の河口域、有数な観光名所である。数十年前から夏になると魚貝類の大量死が頻発していた。1990年に魚を襲って殺すという前代未聞の新種のプランクトン(渦鞭毛藻類、別名ダイノ)が発見された。
このプランクトンは昔から河口域の泥の中で細々と生きていた。ところが燐鉱山の廃水、農業、生活排水などによる河口の富栄養化が格好のお膳立てを用意したことで、その大増殖の引き金が引かれてしまったのである。
この猛毒プランクトン「ダイノ」は24回も姿を変貌することができ、これに襲われた魚は腹部が抉られ食い破られたような状態を呈する。魚の体内で急激の増殖して変貌した「ダイノ」は河川の泥床に戻り、次の餌を狙う。
この猛毒プランクトンは魚貝類を殺すばかりでなく、漁業関係者、一般住民や観光客に対しても危険が迫り、人体にも極めて深刻な健康被害をもたらす。直接触れると、皮膚の腫瘍や下痢、肝臓障害などを引き起す。また空気中に発生された正体不明な物質を吸い込むと運動機能障害のほか、短期記憶の消失などアルツハイマー様症状までもたらすからである。
実証例として、最初は腰のあたりがゾクゾクし、そのうち下半身の血が凍るような寒気に襲われ、手足が抓られるようにキリキリ痛み、筋肉が痙攣して猛烈な火照りが始まるという。
この影響は今日、良好な漁場で、カキなどの養殖の盛んなチェサピーク湾を擁するメリーランド州とバージニア州にも及んでいる。
これは米国のみに発生する問題ではない。日本でも兵庫県西宮の湖沼で「カルガモ」の変死例が起きている。そしてこれはアオコの「シアノバクテリア」の毒性(フグの毒性に匹敵)によるものではないことが判明している。
河川、湖沼、そして母なる海の水質の維持は地球を取巻く大気の汚染防止と共に環境問題の根源的な二本の柱である。
この猛毒プランクトン「ダイノ」対策はいまだ緒についていないが、その研究は着実に進展している。
事例研究: 我が国において上水道の水源の河川から病原性原虫(クリプトスポリジウム)が検出される問題が発生している。(感染すると下痢などの症状を起こす)
平成12年、「鳥取県千代川からクリプト(表流水調査で検出、水道水は問題なし」の新聞記事が掲載された。我が国の多くの個所では在来式の河川水を引き込んだ貯水場からの伏流水(小石や土砂を通して漉されて流出するもの)を上水道に利用しているが、近年、莫大な経費をかけてクリプト対策の化学処理する上水処理施設の建設が試みられ、その建設をめぐって様々な市民運動や議論を呼んでいる。
その五: 「メス化する自然」 (環境ホルモン汚染の恐怖) デボラー・キャドバリー
近年、精巣がんの発生率が急激に上がっているという一つの手がかりから始めて、科学者たちが人間の生殖と健康に悪影響を及ぼしている物質をコツコツと暴いていく道筋を描く。
男の赤ん坊に生殖器の異常が増え、過去五十年間に精子の数が半減したことが欧米で報告された。同じ時期に他のがん、特に、乳がんと前立腺がんが増加している。
一方、野生動物に「メス化」の徴候を示す、あるいは生殖器の奇形、短小化や「性転換」さえおこしている多くの種がみつかる。実験の結果、ヒトや動物に見られる生殖異常の間には共通のリンクがあることが分った。それは女性ホルモン(エストロゲン)の暴露によってって起こる変化である。
レイチェル・カーソンは1962年の著作「沈黙の春」で、1940年代以降、北米五大湖周辺においては、DDTを始めとする化学物質による大規模汚染が野生動物の繁殖力の減少と関連していることを指摘した。 しかしそれがどのようなメカニズムで生殖に異常が生じるのかは必ずしも定説がなかった。
事例の報告は続き、化学物質の暴露を受けた野生動物に生理的な撹乱が生じていた。さらにヒトにおいても上述の精巣がんの増加および精子数の半減のほか、尿道下裂、停留精巣の増加が報告された。野生動物にみられる現象はヒトにも関連しており、今後、ヒトの生殖に深刻な問題が生じるという可能性は容易に考えられる。
この原書(The Feminization of Nature: Our Future at Risk)に再々出てくる用語「Reproductive Health」、即ち、直訳すると「性と生殖に関する健康」を「生殖健康」と訳している。今後、日本でも普遍化する用語となろう。本書は「人類の生殖健康に悪影響を及ぼす環境ホルモンの脅威」を訴えている。
その六 「文明の歴史に及ぼす環境」 (補足)
歴史上の記録から
1816年、「夏のない年」が始まり、ヨーロッパ中が不作になった。各地で暴動が起こり、革命の嵐が吹き荒れた。多くの都市で前例の ない犯罪が 横行し、社会秩序が大きく乱れた。
これは1815年春、インドネシアのサンバワ島のタンボラ火山の一連の噴火によるものであった。地球の大気の組成の変化だった。しかし世界の他の地域への影響が現れるまでに約一年かかった。太陽光線を劇的に減少させ、気温を低下させたのだった。
1983年夏、ヨーロッパ全土と北アメリカの一部には常に霧が発生した。その年の冬はこれまでになく厳しかった。その原因は明らかではないが、同年後半に日本の浅間山が歴史上最悪の噴火を起こし、それが1780年代の異常に寒い時期の主因になった可能性が高い。
1991年のフィリピンのビナツボ火山の噴火も短期間であるが、大きな衝撃を与え、文明による強力な温暖化を一時的に阻止し、そしてオゾン層の破壊を一時的に増大させた。
アメリカにおけるメーン州から西部に向う移民の歴史的記録によると、1816年と17年の異常に寒い春の後に、飢饉の恐れが移住を呼び起こした。この移住とタンボラ火山の噴火による異常な気候パターンの関係が統計により裏付けられている。
1933年1月、アメリカで大きな砂嵐が始まり、断続的に4年以上も続き、作物を台無しにした。多くの人がカリホルニアに逃げるか、あるいは東部に戻っていった。これは「大鍬起し」による農地の深耕が原因で、嵐による土壌の侵食のため起こったものである。
大気の汚染
・1989年、共産主義の崩壊と東欧革命の嵐が静まると、世界中は共産主義社会の公害、特に大気汚染の信じ難い程のひどさに息をのんだ。
・ボーンドでは子供達を定期的に鉱山の地下の奥深くへ連れて行く。地上の大気中の種々のガスと公害源から子供達をしばらくの間、隔離する ためである。
・チェコスロバキアの北方地域では空気がひどく汚染され、政府はそこに10年以上住んでいる人にボーナスを払う。「埋葬費用」と呼ばれている。
・ウクライナでは、この国だけで毎年米国全体の八倍の微粒子を空気中に撒き散らしている。
・モンゴルのウランバートでは、馬乳酒に舞い降りる黒い煤がコップに入らないように注意しながら飲む習慣になっている。
化石燃料(石炭)を多用している中国から偏西風に乗って日本上空に達する亜硫酸ガス、それらに原因する酸性雨の問題を放置して、日本だけで大気汚染防止を図っても「笊に水」の例えと同じである。
他方、大気圏内核実験禁止条約が1960年代に地上での核爆発を中止させて以来、大気中の恐ろしいストロンチウム90の水準が劇的に低下している。
広域的な大気汚染防止対策は全地球的な気候変動を防止することにもつながるものが多いが、しかし一部には逆の効果を呈するものもある。例えば、酸性雨防止のための脱硫、脱硝酸装置は新たなエネルギーを消費し、大気中にさらに炭酸ガスを放出するのにつながる。公害除去装置を併設した発電所も余分な炭酸ガスを生み出す。
その他の参考文献
・「世界の環境危機地帯を往く」 「Earth Odyssey] マーク・ハーツガード
ヒトという生物は、絶滅の危機から回避して生き残ることができるのか。バンコクの排気ガス、中国の垂れ流し工場、 ロシアの恐るべき放射能 汚染、等々を含め、6年の歳月をかけて19ケ国を歩き、そこの生活する人の視点から人類の サバイバルの道を探す。
・「食品汚染がヒトを襲う」 フォックス
・「死の病原体」 プリオン ローズ
・「アジアの雷鳴」 ニコラス・クリストン&シェリル・ウーダン
・「地球の限界」1999 「続・地球の限界」2001 水谷 広(日大生物資源科学部教授)
・「IT汚染」 吉田文和
最先端技術のIT関連産業とは数百にもおよぶ化学物質を使用する「化学的集約度が最も高い産業」で、、その中には極めて高い毒性物質も含 まれている。 そのため煙突もなく一見クリーンに見えるその工場周辺で水環境汚染、土壌・地下水汚染、廃棄有機溶剤の漏洩等の重大な問題 が各地で起こっている。本書はアメリカ、日本、英国、東南アジアにおけるその現状の具体的レポートを含む警告の書である。
・「海洋をめぐる世界と日本」 村田良平」
・「日本人の知らない地球環境汚染」 別処珠玉樹